| NO.147 |
第7章 幕藩体制の動揺 |
|
| 凡例:[1 ](項目)、「2 」(人名)、『3 』(書籍名・作品名) |
|
| 3] |
洋学の発達 |
|
1 |
B[1 ]学 |
|
|
イ |
別名*A[2 ]学(西洋学術の総称)の発達 |
|
|
ロ |
推移-第一段階~第五段階 |
|
2 |
第一段階 |
|
|
イ |
元禄時代 |
|
|
|
① |
ドイツ人医師E「3 」、渡来。E『日本誌』(鎖国論として出版) |
|
|
|
② |
18C初-C「4 」 |
|
|
|
|
a |
D『5 』(長崎通詞時代の見聞録) |
|
|
|
|
b |
E『町人嚢』、E『百姓嚢』 |
|
|
ロ |
正徳時代のA「6 」 |
|
|
|
① |
A『7 』(Sidottiの尋問で得た西洋の風俗記録) |
|
|
|
② |
A『8 』(1715年。世界地理書)→明治時代刊行 |
|
|
|
|
a |
欧の天文・地理は日本が追いつけないほど進歩 |
|
|
|
|
b |
儒教がキリスト教より優秀 |
|
3 |
第二段階(享保時代)-将軍A「9 」のD[10 ]洋書の輸入緩和 |
|
|
イ |
蘭語を研究したB「11 」-E『甘藷記』(甘藷栽培の記録) |
|
|
ロ |
蘭語を研究したD「12 」-吉宗の命で薬物研究 |
|
|
ハ |
洋学-蘭学として研究 |
|
4 |
第三段階 |
|
|
イ |
明和時代のスウェ-デン人EThunberg |
|
|
|
① |
E『日本植物誌』刊行 |
|
|
|
② |
E桂川甫周、E中川淳庵ら師事 |
|
|
ロ |
安永時代(田沼時代) |
|
|
|
① |
*A「13 」(若狭小浜藩医)・*A「14 」(中津藩医)・順庵 |
|
|
|
|
a |
C『15 』(独人クルムスの原書の蘭訳)の翻訳*A『16 』 |
|
|
|
|
b |
1774年-刊行(挿絵-E小田野直武) |
|
|
|
② |
B『17 』(玄白の蘭学創始期の回想録。最初は『蘭東事始』)  |
|
|
ハ |
寛政時代のC「18 」-C『19 』(1793年。西洋の内科書の訳本) |
|
5 |
第四段階 |
|
|
イ |
文化時代の天文方のC「20 」が提唱 |
|
|
|
① |
1811年-*B[21 ](翻訳局)設置 |
|
|
|
② |
フランスのNoel Chomelの百科辞典の翻訳書E『厚生新編』 |
|
|
|
③ |
1885年D洋学所→1856年*A[22 ]→洋書調所→1863年開成所→東京大学 |
|
|
ロ |
文政時代 |
|
|
|
① |
オランダ商館医師*A「23 」(ドイツ人) |
|
|
|
|
a |
A[24 ](長崎郊外の医学塾)開設 |
|
|
|
|
b |
門人-A高野長英、C小関三英、E伊東玄朴(牛痘の接種に成功) |
|
|
|
|
c |
E『日本動物誌』・E『日本植物誌』 |
|
|
|
② |
B[25 ]事件(1828年) |
|
|
|
|
a |
シ-ボルト帰国の時、国禁の日本地図をC「26 ](天文方)より入手 |
|
|
|
|
|
したことが発覚し、シ-ボルトは国外追放、景保は投獄 |
|
|
|
|
b |
シ-ボルト-帰国後、『日本』刊行(高橋の日本地理学を世界に紹介) |
|
|
|
③ |
A[27 ]の獄(1839年。高野長英ら蘭学研究グル-プの弾圧事件) |
|
6 |
第五段階 |
|
|
イ |
天保時代の*B「28 」 |
|
|
|
① |
大坂でB[29 ](人材養成の塾)設立 |
|
|
|
② |
門下生-大村益次郎、橋本左内、福沢諭吉 |
|
|
ロ |
安政時代 |
|
|
|
① |
E種痘館(1858年)→幕府直営D[30 ]所(1860年)→D医学所(1863年)→東京大学 |
|
|
|
② |
1855年-長崎海軍伝習所 |
|
|
|
③ |
1862年-蕃所調所の西周・津田真道、オランダへ留学 |
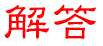 |
|
正解数( )問/問題数(30)問=正解率( )%
|